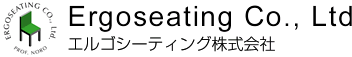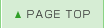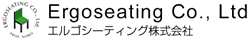靴を脱ぐ装置の試作品
本報告の目的
転倒には履物の影響が大きい。靴の脱ぎ履きなどの動作があるために転倒が起こりやすいことがある。www.space-art.jp/service/rebuilding/
同様の有限会社コパンの報告がある。そこで調査と装置の試作を行った。
予備調査
靴を脱ぐことで困ったことについて、看護学生45名への調査の結果を示す。
質問1 靴を脱ぐことで自分が困ったことがあれば書きなさい。 カッコ内は人数
玄関で脱ぐ時(25)、足がむくんだ時(16)
質問2 靴の種類
革靴(就活靴含む)( 9) ブーツ(23) スニーカ(12)
質問3 どのように困ったか。
よろけそうになった( 23)時間がかかりすぎた(22)
特筆すべき意見
買い物で両手がふさがれた時,片足立ちがあやふく、かがんで脱ぐのも難しい。妊娠中かがんで脱ぎにくい。ブーツが脱ぎにくい。スペースが狭かったり、体を支えるものが無い時。高齢者は筋力低下で安定性が低くなるのでつらいであろう。
靴脱ぎ装置の開発
まず実例を調査した。その結果、次のようなものがあった。
中伊豆リハでの自製具 これは、患者の自立を即するための自助具である。商品として 据え置き型や手持ち型など意外と多い。
杖式としてヌギハッキィイなる名称のものがあった。それぞれ多少の問題点もあるので、独自に靴脱ぎ原理を考え、試作品を作ってみた。
開発原理の構築
靴を脱ぐ手を人工の手に替える。
開発原理と過程 と試作品を紹介、展示を行った。

写真 学会での展示の様子
ガガーリンが宇宙船に乗りこむとき、手の親指と人差し指で円弧を作りそれで靴の踵を抑えて脱いでいた。(NHK宇宙飛行の番組)日本人がこの動作で靴を脱ぐのは、足が靴にぴったり合っていたり、靴ひもでしっかり固定している時に限る。しかし、転倒の防止や中高年令者の腰の前屈の困難さを考えると、靴脱ぎ装置の必要性もあることが判った。
謝辞 中伊豆リハ作業療法士 梶原幸信氏に助言いただいた。感謝する。
引用文献
矢田 茂樹、住居における高齢者の転倒事故、横浜国立大学教育紀要 ; 巻号 : 1997-11, (通号 37)
- 呼吸枕
- 医師用椅子(産医大版)の開発
- 取扱説明書
- 素材の特性から選ぶクッション
- 星観(プラネタリウム)椅子の開発
- 巻きずしロール
- 骨盤ざぶとん
- 仙骨サポート座布団
- 仙骨サポート座布団(SSZ)の効果の検証
- レストランの椅子
- 航空機用シート
- カーナビゲーション用リモコン
- アクセルとブレーキの踏み間違い 研究
- 講演ー実験と製品化人間工学 2017.7
- Ergonomics has an important role to play for supporting economic and industrial activities.
- ダイムラー社ベンツ最新Eクラスのエルゴノミクス体験
- 人間工学入門その1 何のためにあるのでしょうか
- その2 いつ頃から人間のことを考えてものを作るようになったのでしょう
- その3 参加型人間工学
- 講演 人間工学による物作り その1ー5つの鍵
- 講演 人間工学による物作り その2ー事例1キッチンナイフ
- 講演 人間工学による物作り その3ー事例2 椅子
- 講演と論文・記事
- 国家試験問題(人間工学関連)の傾向と対策
- 目次と趣旨
- 第1章 看護のためのエルゴノミクスとは
- 第1章 1.2 人間工学で必要な人体の知識 1.3 ICTの活用
- 第3章 看護師の動きを時間で測る
- 第4章 患者の満足を調べる
- 第5章 病室の患者のゆとりを測る
- 第6章 椅子・パソコンと健康障害
- 第7章 医療ミス